 |
入口には、色画用紙できれいに作って下さった“八角寄席”の看板が。プランターにはいつも、季節のお花が植えられています。 あぁ、いい天気〜、と思いきや・・・ |
 |
今日の岡山は県北部は雪、県南部も最高気温が3℃でいつ雪が降るかわからない、との気象情報でした。準備するメンバーも、寒そうですね。 |
 |
会場準備を終えた所を、受付側からパチリ。お客様は、このような目線で入って来られるのですねー。廊下では、白いウサギの折り紙がお出迎え。近頃の八角園舎は随所にこうした気配りがみられ、女性の館長さんならでは、という気がします。 |
 |
二人は着物談義で盛り上がっています。廣加郎さんが買ったコートの話、メンバーの多くが通う店が閉店する為、最終セールに行った話。着物の話はする相手が限られるので、他のメンバー同士でも、「こういうの、作った!」「欲しいけどなぁ〜。」という会話がよく交わされています。 |
 |
凡々さんの、何に皆注目しているの?既に高座着の人、準備前の人、脱いだコートに帽子・・・くつろぎの楽屋風景です。 |
 |
最近はお客様も大半が常連の方で、しっかり防寒仕様でお越しです。受付では毎年恒例となっている、使い捨てカイロが配られています。 |
 |
紫亭式部さんの『首提灯』で開演です。 上燗屋 → 道具屋 → 自宅、と場面が変わりますが、ご本人の好みでしょうか、上燗屋相手の演技は秀逸です。泥棒が首を押さえながら、斬られたのを自覚する辺り、そこからサゲに至るまでは、大人も子どもも同じように引き込まれていました。 |
 |
高座後は、シュッと着替えて、「ごめん、四時からもう一ヵ所あるから。」と帰って行きました。仕事柄顔が広く、人前に出る機会の多い式部さんは、個人的に落語を頼まれることも増えています。でも、車に乗らない式部さんは、どうやって次の会場へ移動したのでしょう?ハイヤー? |
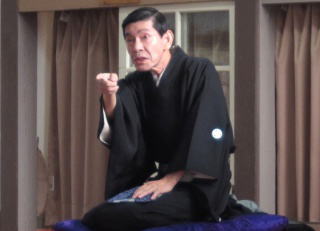 |
二番手は、世間亭廣加郎さん。演題は『親の顔』です。 5点を取った子どもの父親が、学校から呼び出されますが、その回答のユニークさには頭が下がります。大人も子どもにも通用する笑いで、こうした子どもの発想を伸ばす環境を作れば、日本の将来も明るくなるのではないかと感じさせる落語です。 |
 |
中トリは、讃岐家かずのこさんの『花色木綿』です。 この時季いつも、かずのこさんは無事会場入り出来るのか、と心配しますが、今日は本当に雪の中を「滑りながら来た」そうです。でも落語は滑りません。マクラで親戚の十七回忌に昨日行った、という話をしていました。寄席の日の次の日、一月十七日は、阪神・淡路大震災が起こった日です。 |
 |
中入り後は、笑皆亭凡々さんによる『初天神』です。 ご本人都合により、飴玉の所まで演じました。別の機会に、団子の場面が観たいですね。マクラから、お客様も思われたでしょう → ①最上稲荷のみたらし団子が食べてみたい(その場で焼いてくれる)。 ②凡々夫妻は仲がいい(一本の団子を分け合う)。とな。 |
 |
本日の主任は、安里家結太さん。演題は『子は鎹』です。 鎹(かすがい)は、落語を聴かない人にとっては、もう一生縁がない言葉なのでは?この噺は、鎹の意味がわからなければ全くわからないため、マクラで丁寧に説明しています。 |
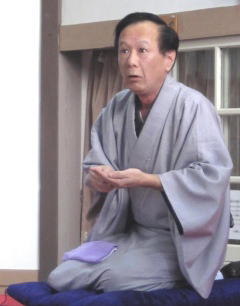 |
親子の情、男と女の心情の機微、当時の長屋や職人の様子・・・と、色んなものがつまった人情噺です。それだけに演者の噺に対する思い入れがストレートに表れますが、お客様の反応からしても、しんみりする所と笑う所のメリハリがきいていました。 |
 |
2011年最初の記念撮影です。極寒の中、お運びいただいたお客様のほとんどが、最後まで残って下さいました。中には廣加郎さんの同級生で某総合病院の院長先生もお越しになり、(ここまで出来る体力があるなら)「もう大丈夫だ。」とおっしゃったとか。 今年も多くの方のあたたかいご声援に励まされ、支えられながら歩んでいく岡山支店です。 |